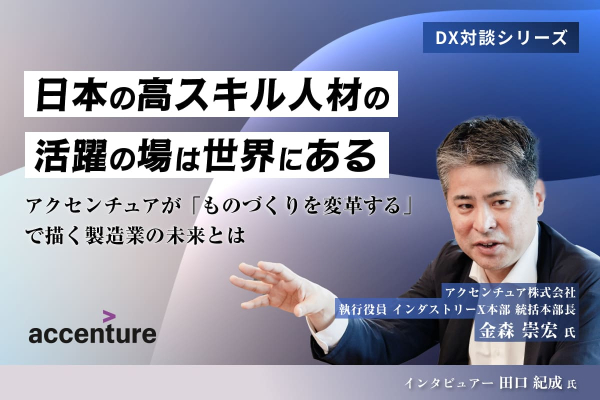
テクノロジーを駆使して、さまざまな業界、領域でサービスを提供する総合コンサルティング会社、アクセンチュア株式会社。2021年、「ものづくりに変革をもたらす」をミッションとするインダストリーX本部を立ちあげ、デジタルを活用した製造業の成長支援を行っています。
「ものづくりDXのプロが聞く」は、Koto Online編集長の田口紀成氏が、製造業DXの最前線を各企業にインタビューするシリーズです。今回は、アクセンチュア株式会社 執行役員でインダストリーX本部 統括本部長の金森崇宏氏に、多くの企業をみてきた経験から感じる日本の製造業の強みと課題、ものづくりの未来について、お話を伺いました。

アクセンチュアで20年以上の経験を保有。製造・流通・小売・運輸などにおいてITから現場の業務改革まで構想からシステム開発、定着化までを幅広く支援。業務領域としても研究開発・生産・物流をもちろん原価管理・販売などバリューチェーンの経験を幅広く保有。現在はインダストリーX本部 統括本部長として日本のものづくりをデジタルを梃にした改革の実現に向けて飛び回る日々。
2002年、株式会社インクス入社。3D CAD/CAMシステム、自律型エージェントシステムの開発などに従事。2009年に株式会社コアコンセプト・テクノロジー(CCT)の設立メンバーとして参画後、IoT/AIプラットフォーム「Orizuru」の企画・開発等、DXに関して幅広い開発業務を牽引。2014年より理化学研究所客員研究員に就任、有機ELデバイスの製造システムの開発及び金属加工のIoTについて研究を開始。2015年にCCT取締役CTOに就任。先端システムの企画・開発に従事しつつ、デジタルマーケティング組織の管掌を行う。2023年にKoto Onlineを立ち上げ編集長に就任。現在は製造業界におけるスマートファクトリー化・エネルギー化を支援する一方で、モノづくりDXにおける日本の社会課題に対して情報価値の提供でアプローチすべくエバンジェリスト活動を開始している。
目次
「ものづくりに革新をもたらす」をミッションに設立されたインダストリーX本部
田口氏(以下、敬称略) 最初に金森さんのこれまでの経歴についてお聞かせください。
金森氏(以下、敬称略) 私が入社をしたのは2000年で、当社の前身であるアンダーセン・コンサルティングの最後の世代として新卒で入社しました。私は社内で「ジョブホッパー」と言われるくらいいろいろな部署を経験しております。テクノロジー部署でシステムのコンサルや開発をしたり、ストラテジー&コンサルティングという部署で戦略づくりをしたり、さまざまな仕事に携わってきました。
また製造流通本部で、OEMを手掛ける企業やサプライヤー、製造設備を作っているメーカーなどのお客様に対して、コンサルティングや業務開発など行うことが多かったですね。当時はほとんどオフィスにはおらず、お客様の研究所や倉庫、それから全国の工場を行脚していました。休憩時間などに個々のプロダクトの誕生秘話や苦労した点などをよく聞かせてもらっていました。アクセンチュアには「本社系のコンサルティング」のイメージが強いかもしれませんが、私の場合は本社系よりも現地を飛び回ることが多かったです。
インダストリーX本部が立ち上がったのは2021年で、ビジネスを拡大していく状況で、製造業をはじめアクセンチュアのさまざまなサービスに携わってきた私の経験が生かせるのではないかということで前任者から引継ぎ、現在、統括本部長を務めています。
田口 御社の中におけるこの部署の立ち位置や役割、ミッションはどのようなものになるのでしょうか。

金森 「ものづくりに変革をもたらす」が組織のミッションです。ものづくりの中には「製造」もありますし、「創造」もあります。私たちがやりたいことを表現するには、日本語の「ものづくり」が一番しっくりきますね。英語で言うエンジニアリング&マニュファクチャリングもロジスティクスもR&Dも、全てを含めた広い意味のものづくりにおいて、改革をもたらしたいと考えています。
それを実現するために、インダストリーX本部には新卒から中途採用で入ってきた経験者、それからM&Aなどで仲間になったベテラン層まで、幅広い人員が在籍しています。職種としても、ビジネスコンサルタントや図面を引くハードウェアのエンジニアなど多方面のエキスパートがそろっています。
経営のデジタルツインを構築し、大胆な判断をサポート
田口 ものづくりに変革をもたらすために、具体的にどのようなことを想定していらっしゃるのでしょうか。製造業の目指す理想の姿はありますか。
金森 目指しているのは、製造業の現場をデジタルツイン化して、業務の効率化だけではなく、いち早く的確な経営判断ができる仕組みを構築することです。現在、ERPやCRMによって事業系のデータに関してはある程度把握ができるようになってきていますが、それだけでは不十分で、現場のものづくりに関するデータが必要不可欠です。ものづくりのデータと事業系のデータが揃わないと、大胆な経営判断をすることはできません。この二つをつないだ経営のデジタルツインを早急に作り上げたいと考えています。

ここをスピード感持って実現するために、外部の力も活用しています。知能ロボット事業を手がける株式会社Mujinと合弁会社(Accenture Alpha Automation株式会社)を立ち上げたり、ドイツの電機メーカー・シーメンスとエンジニアリングや支援体制強化に向けたビジネスグループを設立したり、いろいろなプレーヤーと組んで実行力を強化しています。
「たが」を外してゼロベースから議論ができる土壌づくり
田口 日本の製造業については、縦割りの組織構造や、さまざまな業務・工程が連携できていないなどが課題によく挙げられます。金森さんご自身は、そうした点についてどうお考えですか
金森 確かに「縦割り」とよく言われますが、製造業の方たちからしたら、これは縦割りではなく「分権」なんですよね。ものづくりの一連の流れを考えると、R&D、生産、物流、カスタマーサービスなど、他にもたくさんありますが、とにかく多くの機能が必要です。全てを1人が見ていくのは不可能なので分権しましょう……ということで今の形になってきたのだと思います。これは自然なことではないでしょうか。
今までは自分たちの担当領域に関してしっかりと仕事をすること、例えば工場長であれば自分の工場でしっかりと結果を出すことが至上命題でした。隣の工場がどうなっているのかについては考える必要がない、また口を出すべきことではないからやってこなかったのだと思います。
しかし今、技術が進化し、デジタル化によっていろいろなことができるようになりました。データを使って全社的な変革を目指そうと思うと、横同士連携することが必須となります。
経営層の方にデータを使った改革への取り組みを伺うと、工場長や生産部門の長などに任せているとおっしゃる方がいます。しかし、それでは改革は進みません。例えば生産部門だけに任せると、工場は視野に入るけれどR&Dや物流、営業などは対象外になってしまいます。横同士をつなげるためには、まず経営層から、ものづくりを改革する体制、進め方を考えることが必要です。
田口 分権体制を乗り越えて、横の連携を可能にするには、何が必要ですか。
金森 自分の担当はここまで、という枠を超えられるよう、「たが」を外す必要があると思います。担当範囲に縛られず、ゼロベースで考えていいという前提があれば、現場から出てくる意見をもとに、闊達な議論ができるはずです。しかしその前提がなければ、責任範囲の逸脱だと言われたり、我々の仕事を否定するのかと言われたりするリスクがあります。そうした雰囲気では、大胆な変革につながる意見を出し合うことはできません。
私がプロジェクトに携わる際は、組織のトップの方から、自由に意見を出して大丈夫だ、と現場の方に投げかけてもらうようにしています。この心理的安全性の確保により、最初はゼロベースの意見を出せるのは経営層と一部のマイノリティだけだったとしても、だんだん雪玉が大きくなるかのように現場からの意見も増えていくはずです。会社が存続するため、株主により評価されていくためにはゼロから考える議論が必要だ、とみんなが納得できるプロジェクトは、うまく進みやすいと思います。
同じ事象でも、伝え方で市場の評価は異なる
金森 日本の製造業の現場の方たちは、お世辞でも何でもなく、本当に優秀です。特にR&Dやプロセスを作って量産製造する領域は、とても強いと思います。数字で結果がはっきりと出る極めて厳しい競争社会ですし、年功序列なんていう甘い世界ではありません。それぞれの現場でリーダーとして活躍している人は、そこを生き残ってきて責任ある仕事を任されている方たちです。
それにも関わらず、今、製造業は悲観的な話ばかりが目立っていて、すごくもったいない状況だと思います。強みがたくさんある一方で、「人に伝える」能力が弱いのではないでしょうか。
例えばリストラや国内工場閉鎖の話題があると、現場の人たちの困った声などとともにエモーショナルに報道されることがよくあります。同じ事象でも、経営的に追い詰められた末の苦肉の策として伝わるのと、成長戦略を示した上でそのための必要なステップの一つとして伝わるのとでは、市場の受け止めも働く従業員のモチベーションも大きく異なります。

田口 確かに、変革を迫られる外圧がある中で、厳しい決定をせざるを得ない局面もあるのだろうとは思いますが、背景のストーリーが伝わってこないがために、何だかしぼんだように見えてしまうことがあります。プラスへの変化の兆し、未来への可能性とポジティブに受け止められるような伝え方は大事ですが、できる企業は多くないと感じます。
金森 おそらく経営層の中では、リストラや工場閉鎖の後の成長ストーリーがしっかりと頭の中に入っているはずです。しかし、それを外部や現場の方たちに伝えることが苦手な企業が多い印象です。もちろん、社内外への発信を得意として上手に発信している企業もあります。それができる企業は、市場から評価を得て、社員にも元気を与えることができるのだと思います。
グローバル化は日本の人材にとって大きなチャンス
田口 日本の製造業は停滞していると長らく言われてきましたが現在のマーケットをどのように見ていますか。これからさらにデジタル化が進み、日本の製造業はどのように変わっていくとお考えでしょうか。日本国内だけではなく世界の移り変わりを視野に入れてビジネスをされてらっしゃる中で、将来の日本の製造業の姿について、具体的なイメージがありましたら、お伺いできますか。
金森 日本が人口減少に直面することを考えると、今後は、アメリカや中国、インドなどでいかに売るのか、海外の重要性が増していくと思います。トランプ大統領の関税引き上げが話題となりましたが、そうしたリスクから考えても、現地でものづくりをする必要性が高まり、グローバル化がより一層進むのではないでしょうか。

現地でものづくりをすることを考えると、高品質のものを熟練の従業員ではなくても作ることができる「誰でも」に加えて、海外でも同じく高品質のものが作れるようにする「どこでも」が必要となります。これらを可能にするためにも、先ほどお伝えした、ものづくりの現場のデジタルツイン化が必要になってきます。あわせて、実際の現場では、設計や計画と差異が出てきます。この差異の原因把握に関しても当然ながらデジタル化は有用で、日々の製造現場でデータを取れるようになれば、AIでこの差異を分析していくことが可能になります。
田口 日本の外に出ていかざるを得ない状況がより強まるということですね。そうした動きは製造現場の方たちにどのような影響を与えますか。
金森 グローバル化の流れは、日本でものづくりに携わっている方たちからすると大きなチャンスでもあります。アメリカの製造業で働いている方たちをみると、恐ろしいほど高い給与をもらっています。一方で、当社のクライアント企業で働いている、日本のオペレーターの方たちのQCDSM(Quality、Cost、Delivery、Service、Moral)は素晴らしいものがあるにも関わらず、海外と比べると給与水準がそれほど高くないケースがほとんどです。見方を変えると、グローバル化が進んで人材の流動性が高まっていった際に、高いスキルを持った日本の製造業の方たちは、今よりも良い待遇で力を発揮できる、大きなチャンスでもあると言えるのではないでしょうか。
また、国内にこだわって海外に出ない企業でも、他の企業がグローバル化を進めるなかで、良い人材を取られないよう給与体系などを見直す必要が出てきます。日本のものづくりは良くも悪くも世界に出ていく必要に迫られ、結果としてプラスの方向にアジャストがかかっていくと思っています。
田口 金森さんがおっしゃるような高い現場スキルなど日本の製造業が培ってきた強さ、良い点を残しつつ変革を遂げるためには、何が必要だと思いますか。
金森 一番の鍵は、工場の中から経営レベルのことを考えられる人をどうやってつくるか、ここだと思います。ものづくりのバックグラウンドを踏まえて大胆な経営判断をする人材を生み出すことができれば、大きな変化が起きるのではないでしょうか。
ものづくりに携わってきた方が活躍できる場は、おそらくご本人たちが想像しているよりもはるかに多くあります。そうした方たちが培ったものづくりの知恵をITに変えていくことによって、日本の製造業はもっと競争力を持ち、成長していくことができるはずです。そのためには、国内に閉じずにどんどんと世界に出て活躍していただきたい、それがひいては日本の製造業の未来につながる、そう感じています。
田口 貴重なお話をありがとうございました。

【関連リンク】
アクセンチュア株式会社 https://www.accenture.com/jp-ja
アクセンチュア株式会社 インダストリーX本部
https://www.accenture.com/jp-ja/services/digital-engineering-manufacturing
株式会社コアコンセプト・テクノロジー https://www.cct-inc.co.jp/
【注目コンテンツ】
・100年企業のグローリーがMES導入を3年間で全社展開を成功させた秘訣とは
・エンジニアの精鋭部隊が集結した合弁会社「DTダイナミクス」設立で生産性が3倍に。内製化支援と技術移転、成功の秘訣とは
・【ハノーバーメッセ2025】“製造業×AI”は新たな局面へ、日本企業に求められる変化とは
