目次
社内の問い合わせ対応に追われていませんか?繰り返される質問、属人化した対応、情報の行き違い――これらは多くの企業が抱える課題です。社内FAQの自動化は、AI導入の最初の一歩として最適な領域であり、業務効率化と情報資産の有効活用を同時に実現できます。
本記事では、ChatGPTを活用した最新事例とともに、導入ステップや効果を紹介します。業務改善とDX推進を両立させたい方は必見です。
AIコンサルティングが変える「社内FAQ」の課題と可能性
社内の問い合わせ対応業務は、企業規模を問わずバックオフィス部門に大きな負担を与える業務のひとつです。問い合わせ内容の多くは定型的であるにもかかわらず、担当者が毎回個別対応を余儀なくされており、貴重な人材リソースを圧迫する非効率な構造が生じています。
こうした状況を抜本的に改善する手段として、AIコンサルティングによるFAQ自動化が注目されています。
ここでは、現場で実際に起きている課題と、AIがもたらす可能性について掘り下げていきましょう。
社内問い合わせが増加する現場のリアル
以下のような要因により、社内からの問い合わせ件数は年々増加傾向にあります。
| 主な要因 | 内容 |
|---|---|
| リモートワークの拡大 | 直接の相談が難しくなり、チャットやメールでの問い合わせが増加 |
| 社内制度やツールの多様化 | 勤怠管理、経費精算、福利厚生などの手続きが複雑化 |
| 従業員の入れ替わりや増加 | 新入社員や異動者からの基本的な質問が定期的に発生 |
日常業務に支障をきたすほどの対応負荷に、多くの担当者が頭を抱えています。
属人化・繰り返し対応による業務ロス
現場では以下のような課題が頻発しています。
- 同じ質問への対応が毎月何度も発生する
- 回答が個人依存になり、情報の一貫性が保たれない
- マニュアルやFAQは整備されていても、活用されていない
上記の問題は、ナレッジの分散と非効率な労力の消費を招いており、対応者のモチベーション低下にも直結しています。
AIによるFAQ対応の自動化とは何か
こうした課題に対し、AIによるFAQ自動化は有効なソリューションとなります。生成AI(ChatGPTなど)や自然言語処理技術を用いることで、以下のような対応が可能になります。
- よくある質問に自動で即時回答
- マニュアルや社内ドキュメントの内容をもとに適切な情報を抽出
- SlackやTeamsなどの業務ツールと連携して、利便性を向上
人が対応すべきケースだけにリソースを集中させる環境を整えることで、業務効率と社員満足度の両立が可能になるでしょう。これこそが、AIコンサルティングが提供する新しい社内対応の形です。

社内FAQ自動化がもたらす3つのメリット
社内FAQの自動化は、単なる業務効率化にとどまらず、企業全体の情報流通の質や働き方そのものを改善する施策として注目されています。
特に「繰り返される問い合わせ対応」や「ナレッジの分散」「ハイブリッドワーク環境への対応」といった課題を抱える組織にとっては、導入によって得られるメリットが非常に大きく、バックオフィス業務の変革に直結する投資対象です。
ここでは、自動化によって得られる3つの具体的な効果について見ていきましょう。
問い合わせ対応の工数削減
FAQ自動化により、従業員からの定型的な質問に対する対応時間を大幅に削減が可能です。
| Before(導入前) | After(導入後) |
|---|---|
| 毎回担当者が手動で回答 | AIチャットボットが24時間自動対応 |
| チャット・メール対応が属人化 | 一元化された窓口で即時回答が可能 |
| 月数十時間以上を消費 | 最大70%の工数削減も実現可能 |
限られた人員リソースをより戦略的な業務にシフトできるようになるでしょう。
情報共有の標準化とナレッジ活用
AIによるFAQ対応は、社内に散在する知識を体系化し、誰でもアクセスできるようにするナレッジ基盤の構築にも貢献します。
| Before(導入前) | After(導入後) |
|---|---|
| 回答内容が担当者ごとに異なる | FAQの統一により情報のばらつきがなくなる |
| 古い情報がそのまま共有される | 定期更新とフィードバックで常に最新の情報に |
| 情報が探しづらく利用されない | キーワード検索や自然文質問で即座に参照可能 |
社内の情報資産が有効に活用され、生産性と品質が両立される環境が整います。
働き方改革・リモート対応との親和性
FAQの自動化は、時間や場所に縛られない柔軟な働き方の推進とも高い相性を持っています。
| Before(導入前) | After(導入後) |
|---|---|
| 出社しないと質問・相談ができない | Web・チャットでどこからでもアクセス可能 |
| 対応可能時間が平日日中に限定される | AIが24時間365日応答 |
| 連携ツールが分散し探しにくい | SlackやTeamsと連携し一つの窓口に統一 |
リモートワーク時代に適応した、より自律的で快適な働き方を実現する土台となるでしょう。
AIを活用したFAQシステムの導入ステップ
社内FAQの自動化を成功させるには、単にAIツールを導入するだけでは不十分です。
「人の業務を正しく理解し、AIが適切に代替できる仕組みを段階的に構築する」ことが鍵となります。特にChatGPTのような生成AIを活用する場合、FAQの整理から継続的な改善までの一連のプロセスを踏むことで、精度の高い・実用的なFAQシステムが構築可能です。
ここでは、導入を検討する企業が押さえておくべき3つのステップを探っていきましょう。
よくある質問の整理と構造化
まず最初に行うべきは、社内に蓄積された問い合わせ履歴の分析です。どの部署で・どのような質問が・どの頻度で発生しているのかを把握することで、自動化の対象範囲と優先順位を明確にできます。
| ステップ | 作業内容 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 調査 | 問い合わせログ(チャット、メール、電話など)を収集 | 情報システム部門・総務・人事などから横断的に収集し、パターンを可視化 |
| ② 分類 | 質問をカテゴリごとにグルーピング | 「勤怠・給与」「システム操作」「福利厚生」などに分類し、FAQ構造の軸を定義 |
| ③ 整理 | 回答の内容を標準化・明文化 | 回答に曖昧さや個人の表現が出ないよう、シンプルで一貫性のある言葉に統一 |
このフェーズを丁寧に進めることで、後続のAI学習やFAQの検索性が飛躍的に高まり、ユーザーにとって使いやすいシステムの基盤が整います。
ChatGPTなどの自然言語処理の活用
FAQの土台が整ったら、次に行うのは自然言語処理技術を用いたチャットボットの構築・実装です。
最近ではChatGPT(GPT-4)をはじめとする大規模言語モデル(LLM)が広く活用されており、従来型FAQよりも柔軟かつ高精度な対応が可能です。
| 活用技術 | 概要 | 効果 |
|---|---|---|
| ChatGPT(Custom GPTs) | 事前にFAQや社内マニュアルを読み込ませ、自然文に対する回答精度を高める | 「この件は何課に聞けばいいの?」など曖昧な質問にも対応可能 |
| RAG(検索強化生成) | 社内ドキュメントをAIが参照し、該当箇所を抽出・要約して回答 | 正確な根拠に基づいた回答が可能になり、信頼性が向上 |
| ノーコードツール(Dify、Kibela×LangChainなど) | 非エンジニアでもシナリオ・回答内容の編集や設計ができる | 社内の担当者が柔軟に管理・改善できる運用体制を構築可能 |
ツールを選ぶ際は、「導入のしやすさ」だけでなく、「運用フェーズで社内で自走できるか」という観点で比較検討することが重要です。
継続的な改善による回答精度の向上
FAQシステムは導入して終わりではなく、使われる中で成長させていくプロセスが欠かせません。
回答の質やユーザー満足度を維持・向上させるには、継続的な改善運用が求められます。
| 改善施策 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 利用データの定期分析 | 質問頻度、満足度、未解決率などをダッシュボードで可視化 | 回答精度が低いFAQや新たなニーズを特定し、改善ポイントが明確に |
| フィードバックループの設計 | 「この回答は役に立ちましたか?」などのUI設計で意見を収集 | ユーザー視点での改善ができ、システムの精度と信頼性が上がる |
| ナレッジの更新体制構築 | FAQ更新の担当者・頻度・運用ルールをあらかじめ設計 | 情報の鮮度を保ち、誤回答や古い情報の拡散を防止できる |
このように、「AIの性能」だけでなく「人が改善し続ける仕組み」をセットで設計することが、FAQ自動化を企業内に定着させるための本質的なポイントです。

GeNEEのAIコンサルティングで実現するFAQ自動化
GeNEEのAIコンサルティングは、単なるツール提供にとどまらず、顧客の業務課題に寄り添ったオーダーメイド型のAI開発支援を強みとしています。
社内FAQ自動化においても、まず現場の問い合わせ実態や既存ドキュメントの構成を丁寧にヒアリングし、AI導入に適した業務整理・FAQ構造の設計から伴走します。ChatGPTをはじめとする生成AIの活用はもちろん、検索強化生成(RAG)などの自然言語処理技術を組み合わせ、情報精度と利便性を両立したFAQシステムの構築が可能です。
また、導入後も継続的にチューニングや改善を行い、「使われるAI」として現場定着を支援します。PoC(試験導入)から始められる柔軟なスモールスタートにも対応しており、初めてAIを導入する企業でも安心して取り組める点も特長です。
FAQ自動化は、GeNEEの強みである“業務に即した実践的なAI”の価値を実感できる代表的なユースケースです。
ChatGPTによる社内FAQ自動化の導入事例と効果
ChatGPTをはじめとする生成AIは、すでに多くの企業で社内FAQの自動化や業務ナレッジ活用に実用化され始めています。
ここでは、実際にChatGPTを業務に取り入れて成果を上げている代表的な企業の事例を見ていきましょう。
大和証券|約9,000人がChatGPTを活用、英文レポート要約や資料作成を効率化
大和証券では、グローバルな経済情報や金融レポートの要約・活用に関わる業務効率の向上を目的に、全社規模でChatGPTの導入を開始しました。
- 対象業務:英文レポートの要点抽出、営業資料のドラフト作成
- 活用方法:社内専用の生成AI環境を構築し、ChatGPTが入力文書の要約・翻訳・要点整理を自動で実施
- 利用範囲:全国の営業店を含む約9,000人の社員がアクセス可能
- 導入効果:翻訳作業の時間削減、情報精度の向上、業務スピードの全社的改善
ChatGPTは、情報の信頼性を保ちながらアウトプット品質を維持するツールとして、情報処理業務にかかる負担を飛躍的に軽減しました。
アサヒビール|R&D部門での技術文書検索と要約に生成AIを活用
アサヒビールでは、研究開発部門が保有する膨大な技術資料の検索・整理の効率化を目的に、ChatGPTを導入しました。
- 対象業務:過去の研究報告・技術マニュアル・原料データの調査
- 活用方法:生成AIが自然文での質問に対し、関連技術文書を検索・要約して回答
- 技術背景:資料の文脈理解と要点抽出にRAG(検索強化生成)を併用
- 導入効果:技術者の文献検索にかかる時間を大幅に短縮、属人化していた知識の活用が全社的に可能に
研究開発領域でも、ChatGPTはナレッジ活用と情報整理の自動化という観点から強力な支援ツールとなっています。
三井住友海上火災保険|社内問い合わせ業務をChatGPTで効率化し、文書作成・情報検索を自動化
三井住友海上では、社内向けの問い合わせ対応業務を効率化するため、ChatGPTを用いたFAQ自動化に取り組んでいます。
- 対象業務:人事・経理・法務などバックオフィス部門への定型的問い合わせ対応
- 活用方法:ChatGPTが社内ルール・マニュアルをもとに質問に回答し、関連文書のリンクや参考資料も提示
- 導入スコープ:一部部門で試験導入後、全社展開を検討中
- 導入効果:問い合わせ対応時間の短縮、対応の質の均一化、問い合わせ窓口の負担軽減
AIの導入によって、定型業務にかかる人的コストを大きく圧縮しつつ、社員体験の質も向上させる好事例です。
三菱UFJ銀行|行内ナレッジ共有と定型文生成に生成AIを活用、社内対応時間を大幅削減
三菱UFJ銀行では、行内に蓄積されたナレッジ資産を有効活用し、業務標準化を進める目的で生成AIを導入しています。
- 対象業務:業務マニュアルの検索、定型文(社内メール・報告文)の生成支援
- 活用方法:生成AIが複数の文書を参照し、必要な情報を組み合わせて回答・文案を出力
- 主な成果:検索時間や文書作成にかかる時間を大幅に削減し、属人性の排除とナレッジの再利用が実現
- 将来的展望:FAQ・チャットボット型の展開を他行にも水平展開する動きも
上記の事例は、ChatGPTの導入が単なる業務効率化にとどまらず、組織全体の知識循環を支える基盤となり得ることを示しています。

社内FAQの自動化はAI導入の第一歩
多くの企業にとって、「AIをどこから導入すべきか」は悩ましいテーマです。その中で最初の一歩として最適な領域の一つが、社内問い合わせ対応の自動化、つまりFAQのAI化です。FAQ業務は対象が明確で、既存の履歴データも活用しやすく、効果が可視化しやすいため、PoC(概念実証)から本格導入までのプロセスをスムーズに踏める特長があります。
ここでは、FAQ自動化をAI導入の起点とすることの意義と、実務的な効果について整理しましょう。
小さく始めて社内に成功体験を
AI導入を定着させるには、いきなり全社展開を目指すのではなく、特定部署やユースケースに絞って小さく始めることが重要です。
- よくある質問(例:経費精算、勤怠管理、PC設定)を5〜10件選定し、FAQボットで自動回答を開始
- 一定期間の運用で、「AIでも十分に役立つ」という成功体験を現場に提供
- 現場の声をもとに質問数や回答精度を改善しながらスケール拡張
このように段階的に進めることで、現場の理解と信頼を得ながら、社内全体へのAI活用の意識を醸成することができます。
業務負荷軽減とDX推進の同時実現
FAQ自動化は単なる業務効率化にとどまらず、DX実現の起点としても機能します。
- 定型的な問い合わせ対応がAIに置き換わることで、担当者は付加価値の高い業務へシフト
- AI導入によって社内情報が整理・標準化され、ナレッジの共有と活用が進む
- 対応ログや利用データの分析から、業務フローの改善余地を可視化
このようにFAQ自動化は、目に見える業務改善効果と、組織文化の変革という2つの側面からDXを推進する重要な入口となります。
社内FAQの自動化は今すぐ始められるAI活用の第一歩
AIによる社内FAQの自動化は、業務効率化だけでなく、組織全体の情報活用力や働き方の質を高める確かな手段です。
初期投資や技術的ハードルが比較的低く、既存の問い合わせデータを活用できるため、AI導入の第一ステップとして非常に実用的かつ現実的な選択肢となるでしょう。
今後、より高度なAI活用を進めていくためにも、まずは社内の“よくある質問”という身近な業務から、確実な成功体験を積み上げていくことが重要です。
—————————————————————————————————————
DX/ITコンサルティングからその後のシステム開発・アプリ開発。さらには新規事業立ち上げでお困り事はありませんか? 日本全国には無数のコンサルティングファームや開発会社が存在しますが、企画構想のコンサルティングフェーズからその後の実行支援、そしてシステムの品質(堅牢性や可用性)を意識した設計力・技術力を合わせ持つ会社は、全国で見ても多くはなく、弊社は数少ないその一つ。お客様のご要望通りに開発することを良しとせず、お客様のビジネス全体にとって最適な解を模索し、ご提案ができるビジネス×テック(技術力)×デザインの三位一体型のシステム開発/アプリ開発会社です。ITやDX全般に関して、何かお困りのことがございましたら下記の「GeNEEへのお問合せ」フォームからお気軽にご連絡いただけたらと思います。 GeNEEが手掛けるDX/ITコンサルティング事業
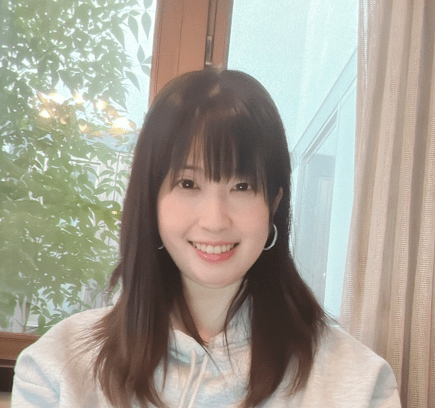
飯嶋シロ
コンテンツマーケティングディレクター
慶應義塾大学卒業後、日系シンクタンクにてクラウドエンジニアとしてシステム開発に従事。その後、金融市場のデータ分析や地方銀行向けITコンサルティングを経験。さらに、EコマースではグローバルECを運用する大企業の企画部門に所属し、ECプラットフォームの戦略立案等を経験。現在は、IT・DX・クラウド・AI・データ活用・サイバーセキュリティなど、幅広いテーマでテック系の記事執筆・監修者として活躍している。
【注目コンテンツ】
・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー
・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性
・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化
