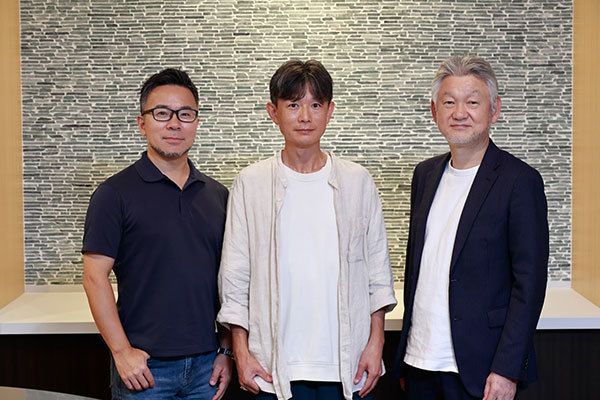
左より田口 紀成氏(Koto Online編集長)、阿野 基貴氏(株式会社電通総研)、福本 勲氏(合同会社アルファコンパス)
今回は「AI Transformation ~電通総研のAI戦略~」をテーマに、Koto Online編集長の田口紀成氏と、株式会社コアコンセプト・テクノロジー(以下、CCT)のアドバイザーで合同会社アルファコンパス 代表CEOの福本勲氏の2人が、株式会社電通総研 クロスイノベーション本部 本部長の阿野基貴氏を招いて、2025年10月8日にウェビナーを開催しました。 今回は、その内容を再構成したダイジェストをお届けします。
阿野 基貴氏
株式会社電通総研 クロスイノベーション本部 本部長
金融・製造・流通/小売・製薬・省庁/自治体などの幅広い顧客向けの国際ネットワークサービスの企画・開発を経て、数多くの基幹・業務システム開発やパッケージソフトウェア開発のプロジェクトマネージャーや全体統括責任者を歴任。
近年は、AI・UX・クラウド・サイバーセキュリティなどの日々進化する先端テクノロジーのR&D/CoE組織※を統括。最先端のデジタル技術を活用したDXを推進し、企業の業務改革や価値創出を支援。
金融・製造・流通/小売・製薬・省庁/自治体などの幅広い顧客向けの国際ネットワークサービスの企画・開発を経て、数多くの基幹・業務システム開発やパッケージソフトウェア開発のプロジェクトマネージャーや全体統括責任者を歴任。
近年は、AI・UX・クラウド・サイバーセキュリティなどの日々進化する先端テクノロジーのR&D/CoE組織※を統括。最先端のデジタル技術を活用したDXを推進し、企業の業務改革や価値創出を支援。
※CoE(Center of Excellence):組織に点在する優れた人材・技術・ノウハウなどを集約し、組織横断的に活用することでDX推進・イノベーション創出・複雑な課題解決などを促進する組織や研究拠点。
福本 勲氏
合同会社アルファコンパス 代表CEO
1990年3月、早稲田大学大学院修士課程(機械工学)修了。同年に東芝に入社後、製造業向けSCM、ERP、CRMなどのソリューション事業立ち上げに携わり、その後、インダストリアルIoT、デジタル事業の企画・マーケティング・エバンジェリスト活動などを担うとともに、オウンドメディア「DiGiTAL CONVENTiON」を立ち上げ、編集長を務め、2024年に退職。
2020年にアルファコンパスを設立し、2024年に法人化、企業のデジタル化やマーケティング、プロモーション支援などを行っている。また、企業のデジタル化(DX)の支援と推進を行うCCTをはじめ、複数の企業や一般社団法人のアドバイザー、フェローを務めている。
主な著書に「デジタル・プラットフォーム解体新書」(共著:近代科学社)、「デジタルファースト・ソサエティ」(共著:日刊工業新聞社)、「製造業DX - EU/ドイツに学ぶ最新デジタル戦略」(近代科学社Digital)がある。主なWebコラム連載に、ビジネス+IT/SeizoTrendの「第4次産業革命のビジネス実務論」がある。その他Webコラムなどの執筆や講演など多数。2024年6月より現職。
1990年3月、早稲田大学大学院修士課程(機械工学)修了。同年に東芝に入社後、製造業向けSCM、ERP、CRMなどのソリューション事業立ち上げに携わり、その後、インダストリアルIoT、デジタル事業の企画・マーケティング・エバンジェリスト活動などを担うとともに、オウンドメディア「DiGiTAL CONVENTiON」を立ち上げ、編集長を務め、2024年に退職。
2020年にアルファコンパスを設立し、2024年に法人化、企業のデジタル化やマーケティング、プロモーション支援などを行っている。また、企業のデジタル化(DX)の支援と推進を行うCCTをはじめ、複数の企業や一般社団法人のアドバイザー、フェローを務めている。
主な著書に「デジタル・プラットフォーム解体新書」(共著:近代科学社)、「デジタルファースト・ソサエティ」(共著:日刊工業新聞社)、「製造業DX - EU/ドイツに学ぶ最新デジタル戦略」(近代科学社Digital)がある。主なWebコラム連載に、ビジネス+IT/SeizoTrendの「第4次産業革命のビジネス実務論」がある。その他Webコラムなどの執筆や講演など多数。2024年6月より現職。
田口 紀成氏
Koto Online編集長
2002年、株式会社インクス入社。3D CAD/CAMシステム、自律型エージェントシステムの開発などに従事。2009年にCCTの設立メンバーとして参画後、IoT/AIプラットフォーム「Orizuru」の企画・開発等、DXに関して幅広い開発業務を牽引。2014年より理化学研究所客員研究員に就任、有機ELデバイスの製造システムの開発及び金属加工のIoTについて研究を開始。2015年にCCT取締役CTOに就任。先端システムの企画・開発に従事しつつ、デジタルマーケティング組織の管掌を行う。2023年にKoto Onlineを立ち上げ編集長に就任。現在は製造業界におけるスマートファクトリー化・エネルギー化を支援する一方で、モノづくりDXにおける日本の社会課題に対して情報価値の提供でアプローチすべくエバンジェリスト活動を開始している。
2002年、株式会社インクス入社。3D CAD/CAMシステム、自律型エージェントシステムの開発などに従事。2009年にCCTの設立メンバーとして参画後、IoT/AIプラットフォーム「Orizuru」の企画・開発等、DXに関して幅広い開発業務を牽引。2014年より理化学研究所客員研究員に就任、有機ELデバイスの製造システムの開発及び金属加工のIoTについて研究を開始。2015年にCCT取締役CTOに就任。先端システムの企画・開発に従事しつつ、デジタルマーケティング組織の管掌を行う。2023年にKoto Onlineを立ち上げ編集長に就任。現在は製造業界におけるスマートファクトリー化・エネルギー化を支援する一方で、モノづくりDXにおける日本の社会課題に対して情報価値の提供でアプローチすべくエバンジェリスト活動を開始している。
(所属及びプロフィールは2025年10月現在のものです)
