
製造業における業務データは、設計図面から生産管理情報まで企業の根幹を支える重要な資産となっています。近年、本社・工場・営業所など複数拠点へのNAS設置が一般的になる中、各拠点への定期訪問や障害時の緊急対応が大きな負担となっているのが現状です。
一方で、システム管理者の人材不足や兼任体制により、専門的なNAS管理に課題を抱える企業も少なくありません。そこで注目されているのが、アイ・オー・データ機器が提供するクラウド型NAS管理サービス「NarSuS(ナーサス)」です。
この記事では、製造業のNAS管理を劇的に効率化するNarSuSの基本概念から3つの主要メリットや導入手順、さらに成功事例まで詳しく解説します。
目次
NarSuSとは?
NarSuS(ナーサス)とは、アイ・オー・データ機器が提供するクラウド型のNAS管理サービスで、インターネット経由でNASの状態を24時間365日監視し、パソコンやスマートフォンから遠隔地の機器状況を確認できます。
製造業では、本社や工場、営業所など複数拠点にNASを設置するケースが多く、各拠点への訪問や電話での状況確認に時間とコストがかかっていました。
NarSuSを活用すれば、離れた場所にある機器の稼働状況やトラブル発生を瞬時に把握でき、現地への移動時間を大幅に削減可能です。
さらに基本機能は完全無料で利用でき、導入コストを抑えながら効率的なNAS管理を実現します。
専門知識がない管理者でも、分かりやすい画面表示とイラスト付きガイドにより、安心して機器管理を行えます。
NarSuSの主要な3つの機能
NarSuSのおもな機能としては、以下の3点があげられます。
- 24時間365日のリアルタイム監視機能
- HDD故障予兆検知・通知機能
- NAS・UPS・外付けHDD統合管理機能
順番に解説していきます。
機能1:24時間365日のリアルタイム監視機能
NarSuSの基本となる機能が、インターネット経由でのリアルタイム監視です。Webブラウザを使用して、社内の離れた場所や支社・営業所に設置されたNASの状態を自席にいながら確認できます。
監視データは1日1回の定期通知に加え、製品の起動後にも自動的にNarSuSデータセンターへ送信されるため、現地への訪問や電話での状況確認が不要となり、機器の状態を正確かつ迅速に把握可能です。
またバックアップの動作状況や装置の稼働情報もグラフ化されるため、時系列での変化も視覚的に理解しやすくなっています。
わかりやすいアイコン表示により、画面上で異常の有無が一目で判断できる設計です。
機能2:HDD故障予兆検知・通知機能
NarSuSの独自技術として、HDDの故障を事前に察知する予兆検知機能があります。
従来のS.M.A.R.T情報に加え、アイ・オー・データ独自の解析技術を組み合わせて異常を検知し、HDD交換のタイミングを通知できるため、突発的な故障による作業負担を回避して、計画的な対応が可能になります。
そのため機材の準備や他部署への案内など、事前準備により業務への影響を最小限に抑えられます。この機能は無償で提供され、NarSuSに登録するだけで利用可能です。
機能3:NAS・UPS・外付けHDD統合管理機能
NarSuSはNAS単体だけでなく、アイ・オー・データ製USBハードディスクや他社製UPSの状態管理にも対応し、システム全体を統合的に監視できます。
UPS接続時はバッテリー残量や内部温度を監視し、バッテリー劣化による停電トラブルを未然に防げ、外付けハードディスク接続時は容量情報やミラーリング設定状況も確認でき、バックアップシステムの健全性を総合的に把握できます。
2018年からはシュナイダーエレクトリックのUPS「Smart UPS SMTシリーズ」にも対応し、管理対象がさらに拡大されました。これらの機能により、データ保護に関わる全ての機器を単一の画面で監視できます。
NarSuSを使用する3つのメリット
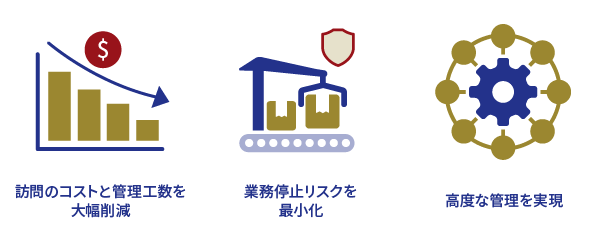
NarSuSを使用するおもなメリットは、以下の3点です。
- 訪問のコストと管理工数を大幅削減
- 業務停止リスクを最小化
- 高度な管理を実現
順番に見ていきましょう。
メリット1:訪問のコストと管理工数を大幅削減
製造業では本社・工場・営業所など複数の拠点にNASを設置するケースが多く、従来は各拠点への訪問や電話での状況確認が必要でした。
しかしNarSuSを導入すれば、Webブラウザを使って日本各地の支社や営業所に設置されたNASをいつ、どこにいても管理できます。現地への移動時間や交通費といった物理的なコストを削減しながら、迅速な対応を実現できるのです。
また複数拠点のNAS状態を一画面で把握できるため、問題が発生した際も即座に原因を特定でき、管理業務の負担が大幅に軽減されます。
メリット2:業務停止リスクを最小化
NarSuSはCPU温度、ファンの回転数、HDDの使用率など全部で7項目をリアルタイムで監視し、異常を検知すると即座にアラートメールを送信します。
しきい値を設定しておけば、ケース内温度の急上昇やファンの停止を事前に察知し、システム管理者が常にNASに張り付いている必要がありません。さらに2017年から開始された予兆通知サービスでは、HDDのべ12万台のビッグデータを活用し、S.M.A.R.T情報とアイ・オー・データ独自技術を組み合わせてHDD故障を予兆段階で検知します。
突発的な故障による生産ライン停止や重要データの消失を防げるため、製造業の事業継続性を大幅に向上させられます。
メリット3:高度な管理を実現
NarSuSの基本機能は完全無料で提供されており、累計登録台数10万台以上の実績を持つ信頼性の高いサービスです。
機器の状態管理、障害発生時の通知と復旧案内、UPSと外付けHDDの管理、HDD故障予兆通知など、高度な管理機能をすべて無償で利用可能です。
またアイ・オー・データ製法人向けNAS「ランディスク」の全シリーズで利用可能で、Linux・Windows OSを問わず対応しているため、既存システムとの親和性も高くなっています。
初期投資やランニングコストを抑えながら、専門的なNAS管理機能を導入できるため、中小製造業でも気軽に高品質なIT基盤を構築できるでしょう。コストパフォーマンスの高さから、多くの企業がNarSuSの存在を理由に導入を決断したケースも報告されており、経営判断としても非常に合理的な選択肢となります。
製造業におけるNarSuS導入の成功事例3選
ここからは実際に、NarSuSを導入した製造業の事例を紹介していきます。
順番に見ていきましょう。
事例1:複数工場を持つ製造業での拠点管理効率化
ある中規模製造業では、本社・主力工場・地方工場の3拠点にNASを設置しており、各拠点への定期訪問や障害時の緊急出張が大きな負担となっていました。
しかしNarSuS導入により、インターネット経由で全拠点のNAS状態を一元管理できるようになり、現地への訪問回数を月4回から月1回に削減。移動時間と交通費の削減効果は年間で数十万円規模に達し、さらに迅速な対応により工場の稼働停止時間も大幅に短縮されました。
システム管理者は自席にいながら7項目ものシステム状態をグラフや数値で一覧確認でき、問題発生時も即座に原因を特定できるため、効率的な運用体制を構築できています。
離島のような遠隔地でも技術者が現地まで駆けつける必要がなくなったという事例もあり、地理的制約の大きい製造業にとって特に効果的なソリューションといえます。
事例2:兼任システム管理者の負担軽減と本業の時間確保
ある製造業では生産管理や品質管理の担当者がシステム管理も兼任するケースが多く、専門知識不足による不安や管理工数の増大が課題となっていました。
しかしNarSuS導入により、ケース内温度の急上昇やファンの停止を事前に察知し、しきい値を超えるとアラートメールを自動送信する仕組みを構築できました。
兼任管理者として常にシステムに張り付いている必要がなくなり、本来の業務に集中できる時間が大幅に増加。トラブル発生時にはメールで通知とガイダンスによる対処方法の案内が届くため、専門知識がなくても適切な対応を取れるようになりました。
ファームウェアの更新なども自動で知らせてくれるため、システム管理の属人化を防ぎ、誰でも安心してNAS運用を継続できる体制を実現しています。
事例3:UPS連携による安定稼働実現
別の製造業では突然の停電や雷などの電源障害が生産ラインの停止に直結するため、UPSとの併用が重要な課題でした。
しかし2018年からシュナイダーエレクトリック製UPSとの連携が開始され、NASとUPSの状態を統合的に監視できるように。結果UPSのバッテリー劣化状態も確認できるようになり、バッテリー運用が必要になった際に電源供給ができないリスクを事前に回避できました。
さらに2024年9月には災害対策を強化するクラウドバックアップサービスも追加されたため、手軽な遠隔地バックアップにより事業継続性を一層向上させることが可能になりました。
NarSuS導入までの3ステップ
製造業でNarSuSを導入するまでの手順は以下のとおりです。
1.事前準備と動作環境の確認
2.NarSuSアカウント登録と初期設定
3.運用開始と効果測定
順番に見ていきましょう。
ステップ1:事前準備と動作環境の確認
NarSuS導入の第一歩として、対象となるNASがアイ・オー・データ製のランディスクシリーズであることを確認します。あわせてインターネット接続環境を整備し、HTTPSポート443の通信が可能かネットワーク管理者と確認しましょう。
プロキシサーバーを使用している環境では、自動設定スクリプトまたは手動設定でHTTPアドレスとHTTPポートの設定が必要になります。
MACアドレスは本製品底面のシールに記載されており、0から9の数字とAからFまでのアルファベットで構成されているため、事前にメモしておきましょう。
またLANケーブルの接続状況も重要で、100BASE-TXまたは1000BASE-T対応のものを使用し、STATUSランプが点灯していることを確認します。
製造業では複数拠点に設置するケースが多いため、各拠点のネットワーク環境を統一的に整備すると導入がスムーズに進みます。
ステップ2:NarSuSアカウント登録と初期設定
NAS管理画面にログオン後、初期画面から「NarSuS登録画面を開く」をクリックして登録手続きを開始します。
初回登録の場合は「NarSuSにはじめて登録(無料)」を選択し、すでに他のNASを登録済みの場合は「NarSuSに製品を追加登録」をクリックしてください。
規約に同意後、ID・パスワード・メールアドレスなどの必要事項を入力し、製品型番・MACアドレス・シリアル番号を正確に登録しましょう。
シリアル番号は製品本体に貼付されたシールで確認でき、MACアドレスはNarSuSアプリ画面に表示される情報をメモしておきます。
登録完了後は登録通知メールが送付されるため、大切に保管してください。
ステップ3:運用開始と効果測定
NarSuS登録完了後、Webブラウザから公式ホームページにアクセスし、登録したIDとパスワードでログインして監視画面を確認します。CPU温度・ファン回転数・HDD使用率など7項目の監視データが表示され、しきい値設定によりアラート通知の調整が可能です。
とくに製造業では、突発的な故障による生産ライン停止を防ぐため、ケース内温度の上昇やファン停止の早期検知設定が重要です。
製造業にNarSuSを導入する際の3つの注意点
製造業にNarSuSを導入する際は、以下の3つに注意しましょう。
- インターネット環境と通信要件の事前確認
- 対象製品の確認
- 拡張機能利用時の追加申請と管理体制構築
順番に解説していきます。
注意点1:インターネット環境と通信要件の事前確認
NarSuS導入時に最も注意すべき点は、ネットワーク環境の通信要件です。
HTTPSポート443の通信が可能である必要があり、製造業で導入が進むUTMやファイアウォールなどのセキュリティ機器により通信がブロックされる可能性があります。
IPv4ネットワークでのみ動作し、IPv6には対応していないため、次世代ネットワーク移行を検討している場合は注意が必要です。
プロキシサーバーを介してインターネット接続している環境では、NAS側のプロキシ設定も必要になります。
また、NASがインターネットに接続できない環境に設置される場合は、別端末でhttps://www.narsus.jpにアクセスして利用コードを取得する手順が発生します。
製造業では機密保持のため厳格なネットワーク制限をかけているケースが多いため、事前にネットワーク管理者との調整が重要です。
注意点2:対象製品の確認
NarSuSはアイ・オー・データ製のLAN DISKシリーズのみに対応しており、他社製NASでは利用できません。
- 製品型番
- MACアドレス
- シリアル番号
の正確な登録が必要で、MACアドレスはNarSuSアプリ画面に表示される情報をメモし、シリアル番号は製品本体のシールで確認します。
ファームウェアバージョンが3.12以前の製品では、最新バージョンへの更新が必須となり、更新作業に時間がかかる場合も。
導入前に対象製品の確認を怠ると、せっかく導入計画を立てても利用できないという事態が発生するリスクがあります。
注意点3:拡張機能利用時の追加申請と管理体制構築
複数台のNAS管理に特化したNarSuS拡張メニューの利用には、別途申し込みが必要で「保守パートナーコード」の取得が前提となります。
拡張メニューでは、
- グループ管理者
- 保守パートナー管理者
- 保守パートナー担当窓口
- お客様アカウント
の4種類のアカウント権限があり、それぞれ機能制限が異なります。
製造業の複数拠点管理では、本社の情報システム部門が管理者権限を持ち、各工場の担当者が参照権限を持つといった階層的な管理体制構築が重要です。
アラートメール送信先は最大5件まで追加でき、管理リストのCSVファイル出力やリモート操作機能も利用できますが、事前の権限設定が複雑になる場合も。
導入後の運用を見据えて、誰がどの権限を持つべきかを事前に整理し、適切な申請手続きを進める必要があります。
NarSuSの今後の展望
製造業におけるNarSuSの展望は、2024年9月に発表されたクラウドバックアップサービスにより大きく広がっています。
従来のNAS監視機能に加え、国産クラウドを活用した遠隔地バックアップ機能が追加され、複数拠点を持たない中小製造業でも本格的なBCP(事業継続計画)対策が可能になりました。
アイ・オー・データは冗長化・ローカルバックアップ・クラウドバックアップという3段階のデータ保護を一気通貫で提供し、目的に応じた安全なデータ保存環境を実現する方針を示しています。
現在約12万台のNAS稼働実績を基盤として、新シリーズの価値訴求とNarSuS登録促進により市場拡大を目指しています。
製造業のデジタル変革が加速する中、NarSuSはオンプレミスからクラウドまでを統合管理する中核サービスとして、顧客企業の状況に合った最適ソリューションを提案していく予定です。
まとめ
NarSuS(ナーサス)は、アイ・オー・データ機器が提供するクラウド型NAS管理サービスで、製造業の複数拠点管理における課題を解決する革新的なソリューションです。
主要な特徴は以下のとおり。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 監視機能 | 24時間365日リアルタイム監視により現地訪問が不要 |
| 予兆検知 | HDD故障を事前察知し、突発的なシステム停止を回避 |
| 統合管理 | NAS・UPS・外付けHDDを一元管理 |
おもなメリットは以下のとおりです。
- コスト削減: 拠点訪問にかかる交通費・移動時間を大幅削減
- 業務継続性向上: 7項目のリアルタイム監視により障害を早期発見
- 高度管理の実現: 基本機能完全無料で専門的なNAS管理が可能
導入時はHTTPSポート443の通信環境確認が重要で、アイ・オー・データ製ランディスクシリーズのみ対応しています。
2024年9月にはクラウドバックアップサービスも追加され、中小製造業でも本格的なBCP対策が実現可能になりました。
累計登録台数10万台以上の実績を持つNarSuSは、製造業のデジタル変革を支える重要なツールとして注目されています。
